文化やアートをめぐるさまざまなこと。
アーツカウンシルしずおかの目線で切り取って、お届けします。
いっぷく

vol.83
「仮装」という最強の心理装置
——掛川百鬼夜行が示す地域・経済・多文化統合の仕掛け
(チーフプログラム・ディレクター 櫛野展正)
掛川城下でポーズを決める若者たち。

彼らは、インドネシア、スリランカ、ネパールからの外国人技能実習生と日本の若者が参加した「掛川と世界をつなぐ妖怪づくりワークショップ」の成果だ。
外国人実習生の多くは、オンライン日本語サロン「いろり」を主宰する幸田穂奈美さんが繋いだメンバーであり、故郷の不思議な存在(インドネシアのクンティラナ、ネパールのクマリなど)と日本の天狗などを組み合わせたオリジナルの「妖怪」を身に纏い、彼らは「掛川百鬼夜行 第四夜」に参加した。
静岡県は製造業や農業が盛んで多くの外国人材が暮らしているが、地域住民との文化的な交流機会は少ないのが現状だ。
このワークショップは、単なる異文化紹介にとどまらず、参加者自身が主体となって故郷の文化を発信し、それを新たな「妖怪」として創造することで、文化的な背景を越えた相互理解と地域への帰属意識を育む、体験型の共生社会モデルを創出している。


これは、静岡県が掲げる多文化共生政策のうち、特に「人づくり」や「居場所づくり」の理念を体現するものであり、今後の施策検討に重要な示唆を与える可能性を秘めている。
この度、当アーツカウンシルが支援する「掛川百鬼夜行 第四夜」を視察し、この事業が、単なる地域イベントの枠を超えた、極めて示唆に富む文化芸術事業のモデルであることを確信した。

約1,800人の来場者と、妖(あやかし)に扮した約150人の参加者が創出したこの熱狂的な成功は、イベントの構造に深く埋め込まれた「参加者を観客から創造の担い手へ変える」という、揺るぎない哲学に支えられている。
イベントの核を駆動する「心理的な安全性」という装置
「掛川百鬼夜行」の成功の鍵は、華やかなイベント風景の裏側にある、「仮装文化」がもたらす、特異な「心理的効用」にあると考える。

狐面などで顔を隠し、非日常的なキャラクター(妖)に成り代わるという行為は、参加者に一時的なペルソナを与える。
これにより、普段の社会的役割や肩書きから解放され、「非日常」という安全な空間の中で、より大胆に、そして自由に自己表現を行うことが可能になる。
内気な参加者であっても、ペルソナを通してイベントに参画しやすくなるという、極めて有効な「心理的バリアフリー」装置として機能している。

この心理的安全性が、冒頭で述べた外国人実習生のような文化的な背景が異なる人々が、抵抗なく交流し、「文化を『共創』(Co-creation)する」という、極めて理想的な相互作用の形を実現している。
さらに、この心理的な安全性が異分野連携のハードルも下げている。

合同会社たゆたう(掛川東病院)による「CPRディスコ」では、DJがCPRに最適とされるBPM110~120のリズムでプレイし、参加者がペットボトルを使ったCPRトレーニングを体験した。
宮地紘樹院長自身も狸に扮してハイテンションで踊りながら実演しており、「参加者の方たちも仮装しているからこそ、ノリノリで参加してくれる」という。
仮装という非日常的な環境が、「誰もが楽しくCPRを学ぶ」という、ユニークで効果的なエンターテイメントを成立させていたのだ。
「熱量の継続性」を生むための担い手創出システム
地域の文化芸術事業における構造的な課題のひとつが、イベント終了後の熱量の一過性だ。
「掛川百鬼夜行」は、この仮装というコアな活動に加え、「掛川百鬼紀行」という創作コンテストという仕組みを組み込むことで、この課題を克服している。

これはイベントの主要な催しというより、仮装という土壌の上で、参加者をイベントの「消費者」から、掛川の地に新たな伝説を書き加える「原作者」へと、その立ち位置を変えるための強力な装置として機能している。
物語という能動的な役割の付与こそが、熱量の源泉なのだ。
こうした哲学が結実した事例として、代表の戸田佑也さんによれば、「掛川百鬼紀行」の表彰式開催後、応募者同士がX(旧Twitter)で連絡を取り合ったり、遊ぶようになったりと、早くも次年度に向けたコミュニティを自発的に形成し始めているのだという。

イベントが終了してもなお、人々の交流と創造的な意欲を継続的に引き出し、育む「コミュニティ形成装置」として機能していることを、この事例は雄弁に物語っている。
地域の文化は、運営側が「供給」するものではなく、参加者自身が創発的に「創り出す」ものだという、本質を突いた哲学が貫かれている。
多分野・多世代を統合するシステム
「掛川百鬼夜行」は、単に人を集めるだけでなく、地域の多様な資源やステークホルダーを統合するシステムとしても優れている。

この心理的安全性の高い仮装文化を基盤に、異分野・異世代の連携が自然に発生した。
伝統文化である遠州横須賀凧チームの参加や、高齢のカメラフリークがイベントの「記録者」として多数訪れた事例は、世代や分野を超えた連携が自然に発生していることを示している。

地域経済との連携も周到だ。
特に、商店街を回遊させる仕掛けは見事であり、年々その連携を深めている。


今回の商店街を巻き込んだカードラリー企画「妖怪商店街めぐり〜隠された呪文を探せ〜」は、子ども連れの参加者を地域の商業空間へ自然と回遊させていた。


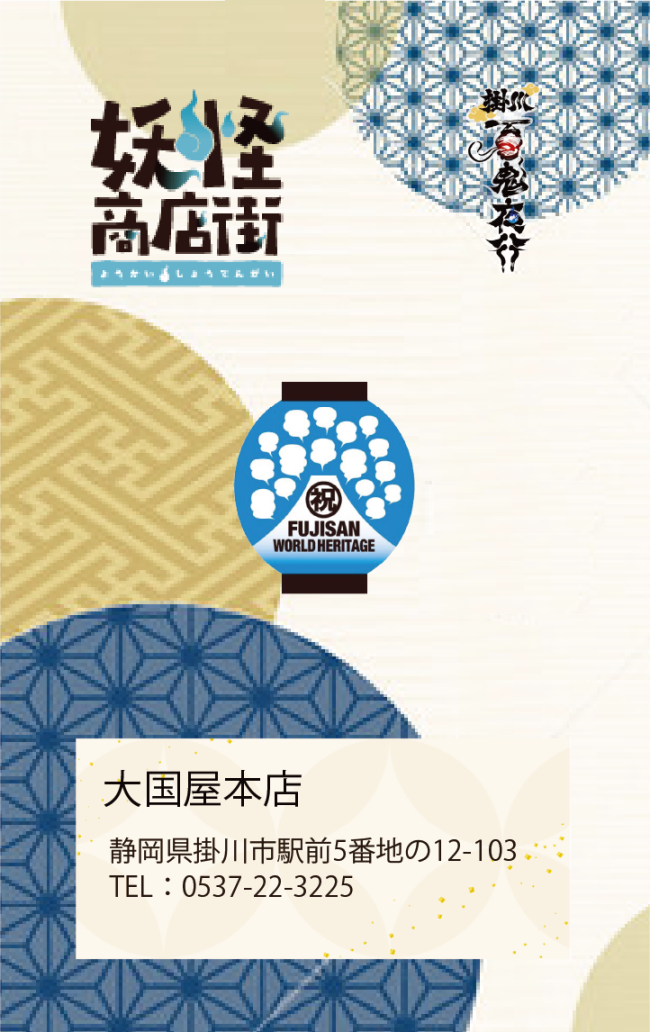
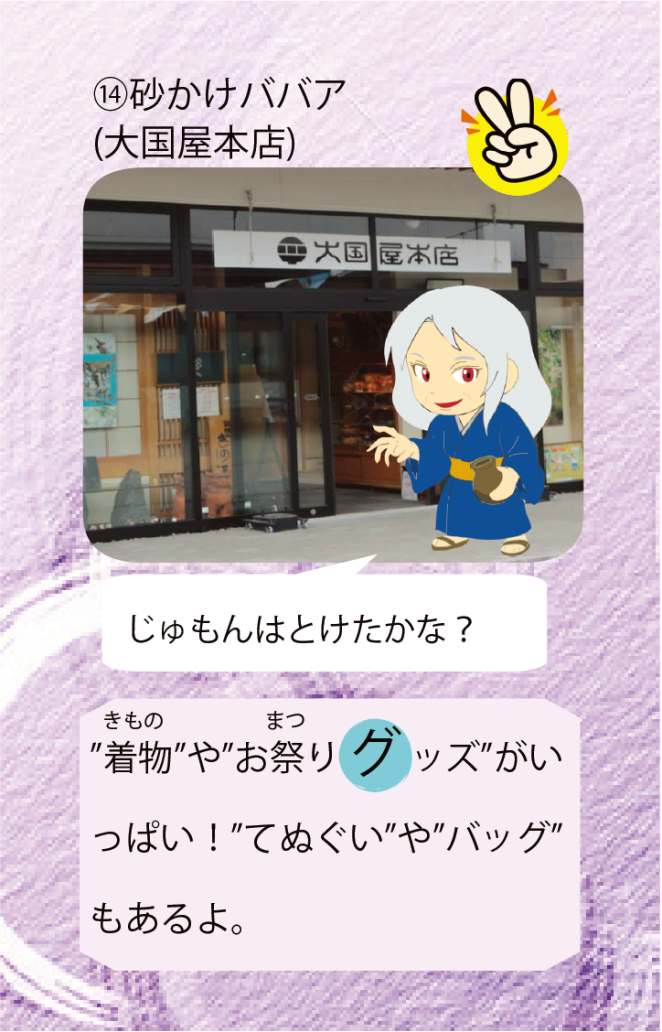
また、地元企業である福田織物による妖怪衣装生地の提供をはじめ、地元店舗が「狐の嫁入り」行列に参加するカップルの着付けを自主的に企画したり、狐面を販売したりするなど、地域商業がこの事業を「自分事」として捉え、能動的に参画している構造を明確にした。

興味深いのは、特に商店街において、本事業の自主企画が次々と生まれている点にある。
「妖怪商店街」は観光協会の提案をきっかけに発足したが、その後は地元商店主とデザイナー、元地域おこし協力隊によって自律的に発展している。
このことは、イベントが単なる集客装置に留まらず、地域での新たな活動のきっかけを生んでいることを示しており、この自主企画の広がりは、代表の戸田さん自身も把握しきれないほどだという。
さらに、掛川百鬼夜行はチーム制を採用しており、戸田さんが各チームに権限を委ねる形で運営を進める自律分散型の運営体制を敷いている。
この組織作りにおける「委任」の哲学こそが、地域における多様な連携と自主企画を生み出す土壌となっているのだ。
これは、地域がイベントの「喜び」を共有し、その価値を自ら拡張しようとする、理想的な文化芸術事業の自走モデルを確立していることを示している。
「掛川百鬼夜行」は、仮装というポップカルチャーを起点に、創造性を媒介として、多文化交流、世代間交流、異分野連携を自然な形で実現している。

次年度に向けて「1000年続けるためのイベント」というコンセプトが打ち出された。
このビジョンは、多様な人々が役割を持ち、分断なく自然に交わる、理想的な地域交流の形を創り出すこの仕組みこそが、地域の創造力を育み、文化芸術の持続可能性を高めるためのモデルケースとして、地域の文化芸術活動のあり方に鮮烈な一石を投じている。





