文化やアートをめぐるさまざまなこと。
アーツカウンシルしずおかの目線で切り取って、お届けします。
いっぷく

vol.52
宙ぶらりんの思考法
(チーフプログラム・ディレクター 櫛野展正)
SDGs(持続可能な開発目標)に代表されるようにサステナビリティの実現が、企業経営においても前提となり、現代は「VUCA の時代」とも言われている。
こうした動きの中で、PROJECT ATAMI実行委員会は「『アート思考による地域課題の解決』をめざした研修・フィールドワーク」を開催した。
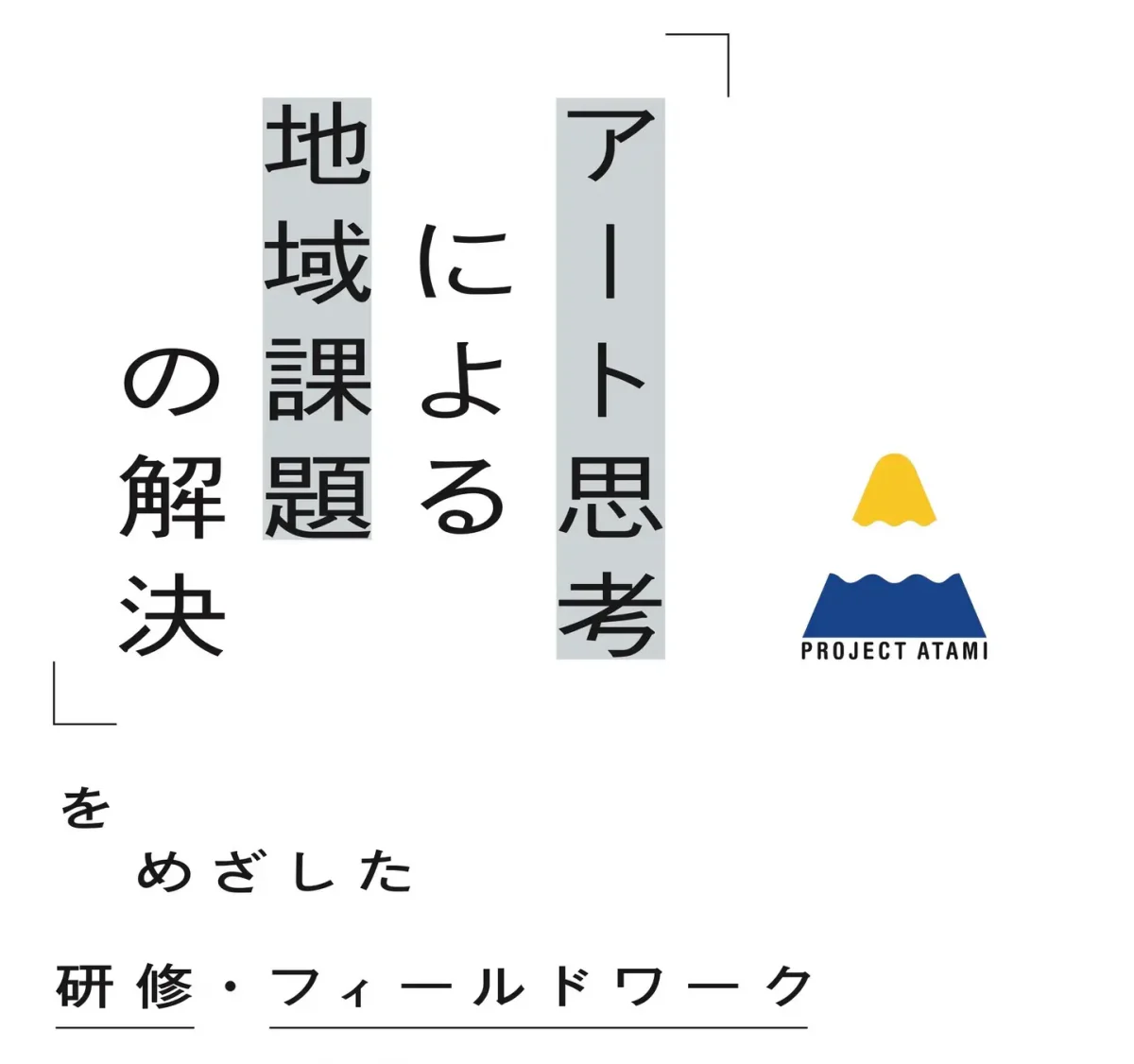
顧客の潜在的なニーズを掘り起こしていく「デザイン思考」は、その限界性も指摘され、近年では新たに「アート思考」が注目され始めている。
「アート思考」とは物事に対して答えを出すのではなく、問いを立てていくための思考法とされており、自分の内側にある興味をもとに自らの物の見方で世界を捉えていくことが重視されている。
個人の内側にある興味関心などといった内発的動機を引き出すためには、アーティストの考えが手本になるというわけだ。

では、アーティストの思考法とは一体何を指しているのだろうか。
例えば、アーティストは作品制作の過程などで、心に留めておいたアイデアの種を掛け合わせ、新たなアイデアを生み出していく。
今回熱海のフィールドワークにおいて、街歩きの案内人となったアーティストの西野達(にしの・たつ)は、公共性の高い場所に私的空間を唐突に出現させ、見慣れた風景を異化してしまうような作品のつくり手として知られている。

こうしたアウトプットの形こそが、各々のアーティストの腕の見せ所であり、僕らが魅了される所以でもある。
一方で、このような表現へ辿り着くために、アーティストは常に作品と対峙しているわけではない。
煮詰まったときには、考えを一旦保留し、作品から離れるために創作を手放すことだってあるだろう。
西野達であれば、それが熱海の街歩きにも繋がっているようだ。

例えば、この原稿を書く過程においても、頭の片隅にぼんやりと執筆のことを意識しながら、コーヒーを飲んだりテレビを眺めたりしているうちに、ムクムクと発想の種が育っていくというわけだ。
これは、前述したアイデアを心に留めておくという行為に他ならない。
つまり、最も大切なのは、拙速な解を求めるのではなく、宙ぶらりんのままで考えを留保しておくことであり、これは「ネガティブ・ケイパビリティ」という言葉に集約される。
ネガティブ・ケイパビリティとは、詩人のジョン・キーツによって生み出され、精神科医のウィルフレッド・ビオンによって再評価された概念で、「性急に証明や理由を求めずに、不確実さや不思議さ、懐疑の中にいることができる能力」のことを指している。
まさに、先の見えない混沌とした現代に求められる能力(ケイパビリティ)と言って良いだろう。

こうしたネガティブ・ケイパビリティを練成するには、すぐに答えを出そうとする姿勢そのものを改めていく必要がある。
これが簡単そうに見えて、意外と難しい。
現代は、スマホで調べれば、知りたいことが何でも検索できる便利な世の中になった。
もちろん、それ自体が悪いことではないのだが、検索結果の先にある問題解決力や創造力を失わせてしまう恐れが問題視されている。
加えて、VUCAの時代には、さまざまな予測困難な事態が生じている。
それらを完全に回避することは不可能であるため、自らで耐え忍ぶ必要があるのだが、そのときに精神的バリアとなってくれるのが、ネガティブ・ケイパビリティの存在だ。
そんなネガティブ・ケイパビリティを鍛えるためには、アートに触れることが良いとされている。

なぜならアートとは、そもそも理解するものではなく感じるものだからだ。
「アートはよく分からない」。
そんな声を、ときどき耳にする。
しかし、アートの真の豊かさとはそうした「訳の分からなさ」さえも許容してしまう懐の深さにあるのではないだろうか。
分からないものを分からないまま受け入れることで、必然的に「なぜ、このような表現をするのか?」という問いが湧き上がってくる。
つくり手の心に寄り添い、まるで卵を孵化させるように心の中で大切に疑問を育てていくことで、他者への共感力が培われていく。
ただ、注意しておかなればいけないのは、あくまでアーティストは問いを投げかけてくれる存在に過ぎないということだ。

ローカルアクティビストの小松理虔は著書『新復興論』の中で次のように述べている。
「アーティストとは、やはり課題を提示する人たちだ。課題を解決するのはアーティストではない。私たちの仕事である」と。
PROJECT ATAMI実行委員会が仕掛ける取り組みによって、これから熱海の街にどんなプレーヤーが生まれるのだろうか。
そのときを期待して待ちたいと思う。






